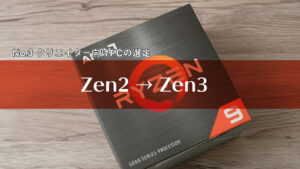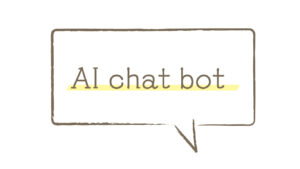最近、ホームページに注力する中小企業様が増えたりして、どうにかしてクライアントと接点を持つよう考えている方が多くなっています。その中で「AI チャットボット作って!」という依頼が増えてきたので、ここに共有。
技術的に云々というよりは、導入に向けての云々を掲載しています
AI チャットボットを導入するメリットとデメリット
ホームページ上にAIチャットボットを導入して運用するにはいくつかのメリット・デメリットがあります。
メリット
- 業務の効率化
- コンバージョン率の向上、インサイトの発見
業務の効率化
電話・メール対応の人件費のカットが見込まれます。年間300万円ほど下げることができるといわれています。営業や正社員の場合は人件費カットだけではなく作業を「営業活動」に専念させることが可能になります。また、頻繁な電話が苦手という方もチャットサポートだと受け入れやすいとかあります。あとは在宅勤務という形式をとることもできます。
コンバージョン率の向上、インサイトの発見
徐々にホームページの内容が肥大化しているのをひしひしと感じています。来訪者が目的のページにたどり着くことが難しくなっています。可能な限りたどり着けるようにサポートするのもチャットボットの役割。検索ツールとしても役にたちます。
インサイト(ニーズ)の発見が可能です。AIチャットボットを利用した場合、入力内容は全て保存されます。それを元に顧客動向をつかむことができます。
デメリット
- 導入&ランニングコスト
- コンバージョン率の低下
導入コスト
導入コスト→システム屋さんに支払う(数万円~100万円以上まで導入ゴールによってことなります)
ランニングコストが発生します。数千円~数万円まで規模やシステムによって異なります。
コンバージョン率の低下
メリットでコンバージョン率の向上を上げたのに、低下もするんですか?という疑問。支離滅裂状態。チャットボットなのでどうしてもボットシステムがあるが故に回答が単純になりがちです。ホームページへの来訪者が本来待っていた回答を得られないとコンバージョン率が低下します。
ボット(bot)とは、robotのことで自動化のことをいったりします。
wikipedia 参照
AI チャットボットを導入する前に準備したほうがよいもの
さぁ導入するぞ!となったときに必要なものがあります。
それは「FAQ、クライアントとのやり取りといった履歴」です。
とにかくFAQ(質疑応答集)は絶対に用意してほしい。事前に用意があるとスムーズにチャットボットの導入を行うことができます。
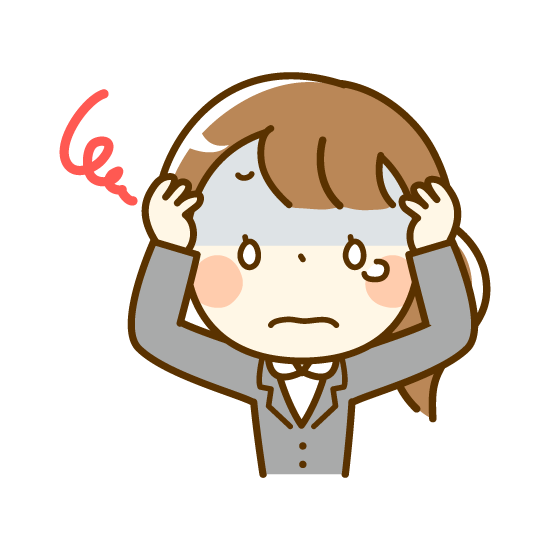
FAQや、やり取りの履歴がなかったどうしたらいいの?
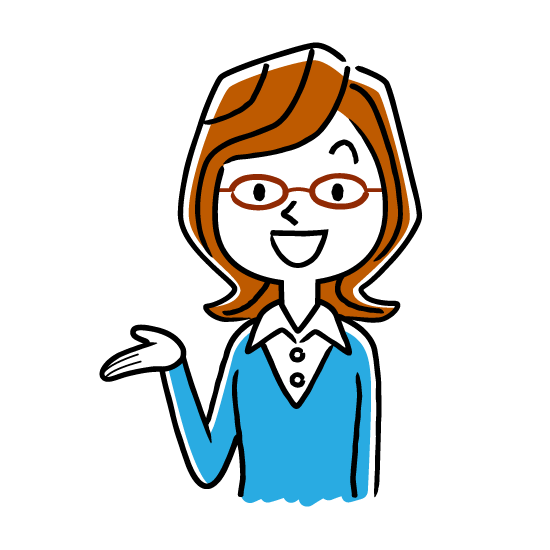
これを機に作りましょう。そして履歴を残して今後のフィードバックとしても活用しましょう。もし、社内対応マニュアルがあるなら、マニュアルをベースにFAQを作りましょう
システムを作る側として「FAQまで作って」といわれることがたまにあるのですが、さすがに「私がつくっていいんですか?」となることもあります。ホームページ上にFAQが準備されていてそこから引っ張ってくる場合はまだ作業としては簡単なものです。
そんなこともなく、クライアントのサービスを0から調査して精査、FAQを想定して作成するとなると、作業量が膨大になり作業が膨大になると費用も膨大になります。
チャットボット導入の時につけておきたい機能
- カスタマーサポート(人)に接続する機能
- 会話履歴を記録する機能(データ抽出できるやつ)
- 日本語対応
カスタマーサポート(人)に接続する機能
回答に満足できない、そのまま手続き移行したい場合といった、柔軟な対応ができるのは「人」です。「人」に接続する機能があると便利◎
ただミスタイプには気を付けないといけませんね。
会話履歴を記録する機能
履歴をもとに調整をするので必須です。これがないチャットボットサービスって無いとは思うのですが、たまに無料だったりするとない場合があるんですよね。
日本語対応
日本のクライアント向けだと日本語対応していないと難しい…だいたいのチャットボットは対応しています。
まとめ:AIチャットボットを導入するときは準備を!
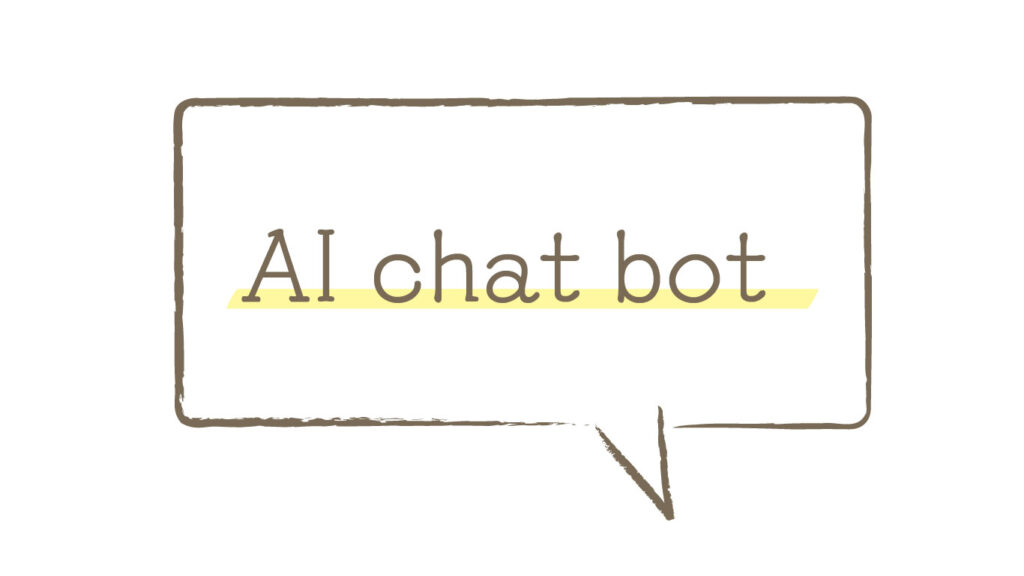
とにかく、FAQなどを事前に準備にすることで非常にスムーズにチャットボットの導入が進みます。工期も短くなるのである程度製作費を抑えることも可能かと思います。準備ができているのであればシステムに強いフリーランスに設定してもらうのもアリです。
あえて、製品名などを出しませんでしたが個人的にはチャットツールとFAQ、欲しい機能が揃っている「Zendesk」あたりが勝手が良いと思います。EC限定なら、ShopifyのGobotとかその辺ですかね。知識やAPIの技術があるならIBM Watsonなども活用できると思います。
どうしても、導入費&ランニングコストが発生する製品がゆえに導入を踏みとどまっている中小企業の方が多いと思いますが、思った以上に費用が掛からないというのが私としては思ってます(オリジナルのホームページよりははるかに安く済みます)
次回は運用してみた編です